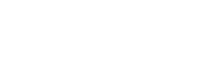当サイトのリンクには一部プロモーションを含みますが、一切その影響は受けず、公正・中立な立場で制作しております。
2025年6月、アップルはAI研究における重要な論文「The Illusion of Thinking: Understanding the Strengths and Limitations of Reasoning Models via the Lens of Problem Complexity」を発表しました。この論文は、AIが本当に「考えている」のか、それとも「考えているように見えるだけ」なのかを調べたものです。この記事では、論文のポイント、AIの課題、そしてこの研究がどんな影響を与えているかを分かりやすく説明します。
論文の概要
アップルの論文「The Illusion of Thinking」は、AIの「考える力」を調べるために書かれました。AIには、普通の大型言語モデル(LLM)と、もっと賢く「推論」できると言われる大型推論モデル(LRM)の2種類があります。この論文では、AIにハノイの塔やチェッカージャンプといったパズルを解かせて、どれくらいちゃんと問題を解決できるかをテストしました。

簡単に言うと、AIは簡単な問題やちょっと難しい問題ならスイスイ解けます。でも、めっちゃ難しい問題になると、急に失敗しちゃうんです。これを「複雑性崩壊」と呼びます。たとえば、ハノイの塔というパズルで、ディスクが10個以上(1023手以上)になると、AIは正しい答えを出せなくなります。まるで「もう無理!考えるのやめた!」って感じになるんです。
この論文は、AIが「考える」と言っても、実はデータの組み合わせを覚えて使っているだけで、本当に頭で考えているわけじゃないかもしれない、と指摘しています。だから、SF映画に出てくるような、なんでもできるスーパーAI(人工汎用知能、AGI)を作るのは、今の技術ではかなり難しい、というのが結論です。
さらに、今のAIのテスト方法にも問題があると書いています。数学やプログラミングのテストは、AIが答えを「覚えちゃってる」場合があって、本当の賢さを測るのが難しいんです。アップルは、ハノイの塔みたいなパズルを使ったテストの方が、AIの「考える力」をちゃんとチェックできると提案しています。この研究は、AIの限界を明らかにして、もっとすごいAIを作るには新しい方法が必要だと教えてくれます。
どんなことがわかった?
論文では、AIのテスト結果からいくつか大事なことがわかりました。以下に、わかりやすくまとめてみます。
めっちゃ難しい問題、たとえばハノイの塔でディスクが10個以上になると、AIは全然ダメになります。LRMもLLMも、複雑すぎる問題だと正しい答えを出せません。これを「複雑性崩壊」と呼ぶんです。AIは、簡単な問題やちょっと難しい問題なら得意だけど、超難しい問題だと「わからない!」ってなっちゃうんです。
AIは、問題が難しくなると最初は一生懸命考えます。でも、めっちゃ難しくなると、逆に考えるのをやめちゃうんです。たとえば、たくさん計算できる時間やパワーがあっても、「もういいや」って感じで手を抜くことがあります。これは、AIが本当に深く考えているわけじゃなく、決まったパターンに頼っているからかもしれない、っと論文に書かれています。
AIは、たとえばハノイの塔の解き方を教えても、毎回ちゃんと使えなかったりします。パズルが変わると、急に下手になったり、やり方がバラバラになったりするんです。これは、AIが「これが正しい解き方!」ってルールをしっかり持っていないから、ってことです。
研究では、問題の難しさによってAIの得意・不得意が3つに分かれることがわかりました:
| 難しさ | どんな問題? | AIの結果 |
|---|---|---|
| 簡単 | ハノイの塔で1~3個のディスク | 普通のLLMがLRMより上手。考える時間がいらない。 |
| 中くらい | ハノイの塔で4~7個のディスク | LRMがたくさん考えて上手く解ける。 |
| 超難しい | ハノイの塔で10個以上のディスク | どっちも失敗。LRMは考えるのをやめちゃう。 |
この表を見ると、LRMは中くらいの難しさで一番強いけど、超難しい問題だと全然ダメってことがわかります。
この研究がAIにどんな影響を与える?
この論文は、AIについて「ちょっと期待しすぎかも」って気づかせてくれる大事なものです。以下に、どんな影響があるかを説明します。
- AIの「考える力」を疑う
OpenAIやAnthropicみたいな会社は、「うちのAIはめっちゃ考えるよ!」って言っています。でも、この論文は「それ、実は考えてるふりかもよ」って指摘してるんです。AIは、データの組み合わせをうまく使って賢く見えるけど、本当に人間みたいに考えるわけじゃないかもしれない、ってことです。 - テスト方法を見直す
今のAIのテスト(数学やプログラミングの問題)は、AIが答えを覚えちゃってるせいで、ほんとの実力を測るのが難しいんです。アップルの研究は、ハノイの塔みたいなパズルを使ったテストがもっと信頼できるって教えてくれます。これから、AIのテスト方法が変わるかもしれません。 - 新しいAIの作り方が必要
今のAIは「トランスフォーマー」っていう技術を使っています。でも、この技術には限界があるみたいです。もっと難しい問題を解けるAIを作るには、全然新しいアイデアや技術が必要だって、この論文は言っています。
みんなの反応
この論文について、AIの専門家やネットの人たちはネット上でいろんな意見を言ってます。
- AIはパターンを使ってるだけ:ネットの掲示板(Hacker News)では、「AIは本当に考えるんじゃなくて、データの組み合わせを使ってるだけ」って意見が多くて、論文に賛成する人がいます。「AIが難しい問題で失敗するのは、人間とは全然違う理由だね」って人もいました。
- 役に立つ場面もある:AIが完璧じゃなくても、プログラミングの手助けやデータの整理みたいな仕事では十分役立つ、って評価もあります。
- パズルが悪い?:ある専門家(sean goedecke)は、「ハノイの塔みたいなパズルは、AIの考える力をちゃんと測るテストじゃないよ」って言っています。AIが「考えるのをやめる」のは、問題の作り方が悪いからかもしれない、ってことです。
- ちょっと大げさ:論文がパズルにばかり注目しすぎて、数学やプログラミングみたいな他の分野でのAIの強さを軽く見てる、って意見もあります。
みんなが話している中で、こんな提案が出ています:
- ルールを使うAI:AIに、数学の公式やルールみたいなものを組み合わせて考える力を足すと、もっと賢くなるかも。
- 新しい技術:今のトランスフォーマーじゃなくて、全然新しいAIの作り方を考える必要がある。
- スーパーAIはまだ遠い:SF映画みたいなスーパーAI(AGI)は、すぐには作れなさそう。もっとすごい発見が必要だね、って声もあります。
AIを使う人へのアドバイス
この論文から、AIを使う人や作る人に役立つヒントをいくつか紹介します。
- AIの限界を知ろう
AIは、超難しい問題だと失敗しやすいです。AIを使うときは、どんな問題なら得意か、どんな問題だとダメかを知っておくと良いよ。 - 答えをチェックしよう
難しい問題をAIに解かせたときは、答えが本当か自分で確認するのが大事。AIが「もう無理!」ってやめちゃうことがあるからね。 - パズルでテストしよう
ハノイの塔やチェッカージャンプみたいなパズルは、AIの「考える力」をちゃんと測るのに役立つよ。AIを試すときは、こういうテストを使ってみると良いかも。
まとめ
アップルの「The Illusion of Thinking」は、AIが本当に「考える」のかどうかを考えるきっかけをくれました。AIは、簡単な問題や中くらいの問題ではすごいけど、超難しい問題だと失敗しちゃいます。この研究は、AIのテスト方法を見直したり、もっと賢いAIを作るための新しいアイデアを考えたりするのに役立ちます。
AIの未来はまだまだわからないけど、この論文は「AIって実はこんな限界があるんだよ」って教えてくれる大事な一歩です。AIが本当に「考える」のか、それとも「考えてるふり」なのか、これからの研究でどんどん明らかになっていくよ!