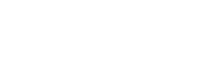当サイトのリンクには一部プロモーションを含みますが、一切その影響は受けず、公正・中立な立場で制作しております。
現代では、多くのウェブサービスでパスワードを求められ、「また新しいパスワードを考えなきゃ…」「あのサービスのパスワードって何だっけ?」と悩んだ経験はありませんか。安全なパスワードを作成し、便利に管理することは、ITに詳しい人も詳しくない人も、全ての人にとって非常に重要な課題です。
「みんなどうやってパスワードを管理してるんだろう?」
この答えがきっと見つかります。この記事では、初心者向けに最新のパスワード生成と管理の方法をわかりやすく解説します。
危険なパスワードの例とその問題
まず、どんなパスワードが危険なのかを押さえておきましょう。以下のようなパスワードは第三者に推測されやすく、非常に危険です。
- 個人情報系: 自分や家族の名前、誕生日、電話番号などその人に関連する情報(他人から簡単に類推可能)
- 短すぎるもの: 桁数が少ないパスワード(桁数が少ないほど短時間で解読されます )
- 単純なパターン: 例: 「1111」「1234」「abcd」「qwerty」などの連番やキーボード配列
- 辞書にある単語: 「password」「apple」「cat」など意味のある単語そのもの(長くても辞書攻撃で突破されます )
- 初期設定のまま: 製品やサービスのデフォルトパスワードを変更せず使っている
- 使い回し: 複数のサービスで同じパスワードを使い回している
もし上記に当てはまるものがあれば、すぐに見直しましょう。特にパスワードの使い回しは厳禁です。不正ログインの被害では、他サービスから流出したパスワードで試行されるケースが多く、IPA(情報処理推進機構)も「サービスごとに違うパスワードを設定する」ことを強く推奨しています。ある調査では、8割以上のユーザーがパスワードを使い回している実態が報告されています。これは非常にリスクが高い習慣です。
安全なパスワードを作るコツ

安全なパスワードのポイントは、第三者に推測されにくく、自分は覚えやすいものにすることです。具体的には「できるだけ長い文字列」にし、「英大文字・小文字、数字、記号」を組み合わせてランダム性を高めます。IPAによれば15文字程度を目安にすると安心です。長く複雑にすると覚えにくくなりますが、工夫次第で覚えやすさと安全性を両立できます。
人間は無意味な文字の羅列より、意味のあるフレーズの方が覚えやすいものです。そこで、自分だけが知る日本語のフレーズなどを活用し、それに変換ルールを加えて強力なパスワードを作る方法があります。
手順は次のとおりです。
- 好きなフレーズを選ぶ: 趣味や好きな歌の一節、座右の銘など、自分にとって覚えやすい日本語の文章を1つ決めます。例えば「うさぎと亀」(童謡の一節)や「青巻紙黄巻紙赤巻紙」(早口言葉)など何でもOKです。ポイントは辞書に載っていない独自のフレーズであること 。下記の例では、「うさぎと亀」→ 独自のイメージ「油断したな!うさぎ」を使いました。
- フレーズを変換する: 選んだフレーズをローマ字表記に直し(もしくは各単語の頭文字を取るなど)、自分なりのルールで一部文字を加工します 。例えば、以下のような工夫が考えられます:
- 一部の文字を大文字に置き換える(例:「yudanshitanausagi」を「yUdAnShItAnAuSaGi」のように2文字目ごと大文字にする)
- 似た見た目・発音の数字や記号に置き換える(例:「a」を「@」、「i」を「1」、「g」を「9」にする 。また日本語の音に合わせて「し」を「4」に置き換えるなど音韻で数字に変換する手法もユニークです)
- 子音だけ残す・特定の母音を抜くなど文字を削除する(例:「ゆだんしたなうさぎ」→ローマ字「yudanshitanausagi」→母音を除いて「ydnstnsg」にする)
- 語尾に記号や数字を追加する(例:フレーズ変換後の末尾に「!」「?」や好きな番号を付け足す)
- 必要に応じて条件を満たす: サービスによっては「記号必須」「大文字必須」などの条件があります。上記の変換ルールの中で、自分のパスワードに大文字や記号・数字が最低1つは入るように調整しましょう。Apple IDなどは大文字・小文字・数字を全て含む必要があるため、例えば「必ず◯文字目を大文字にする」ルールなどを決めておくと確実です。
この方法で「覚えやすい日本語フレーズ+自分ルール」からパスワードを作れば、一見ランダムな文字列でも自分には意味があるため覚えやすく、他人には推測しづらい強力なパスワードが出来上がります 。例えば、先ほどの「油断したなうさぎ」のフレーズもルール変換すれば「yDn4tNsG」のような一見意味不明な文字列になります。しかし自分は元のフレーズとルールを覚えているので、それほど苦労せず思い出せるでしょう。
パスワードそのものより「作り方(ルール)を覚える」方が大切です。仮にパスワード自体を一時的に忘れてしまっても、作り方さえ覚えていれば再現が可能なので、完全に思い出せなくなるリスクを大幅に下げられます。そのため、パスワード帳を作るにしてもパスワードの文字列そのものではなく、作成ルールを自分にだけ分かる形でメモしておくのが良いでしょう。
上記のように自分で工夫してパスワードを作る方法もありますが、専門のツールやサービスに任せてしまうのも賢い手です。最近のパスワード管理アプリやブラウザには、英数字や記号を組み合わせたランダムな強力パスワードを自動生成する機能があります。こうした自動生成機能を使えば、手間なく推測困難なパスワードを作れるので非常に便利かつ安全です。
例えば、LastPassや1Passwordといったツール、あるいはChromeやSafariなどブラウザのパスワード提案機能でワンクリックでランダムなパスワードを得ることができます。
もちろん、自動生成したパスワードは人間には覚えづらいですが、それで問題ありません。後述するパスワード管理アプリに保存しておけば、ユーザー自身が覚える必要はなく、コピーペーストや自動入力で使えるからです。
★ポイント: 絶対にパスワードの使い回しはしない!
どんなに強力なパスワードでも、複数サービスで使い回せば一箇所の漏洩で他も危険に晒されます。自分ルールで作る場合はサービスごとに必ず一部変化を入れましょう(例:サービスごとのキーワードやイニシャルを含める )。ツールで自動生成する場合は各サービスで常に別々のランダムパスワードを発行してください 。使い回しの防止こそが最重要です。
パスワードの安全な管理方法

せっかく強力なパスワードを作っても、管理がずさんでは意味がありません。ここでは複数のパスワードを安全かつ便利に管理する方法を紹介します。基本的には以下の4つが代表的な管理方法です。
- パスワード管理アプリを利用する – 専用のソフトウェアやスマホアプリにすべてのID・パスワードを暗号化して保存し、必要時に自動入力させる方法です。もっとも安全で便利な方法の一つです。代表的なツールとして「1Password」「LastPass」「Bitwarden」などがあり、これらを導入すれば人間がパスワードを覚える必要自体がほぼ無くなります。スマホやPCの生体認証(指紋や顔)でアプリを解錠し、自動入力するだけなので初心者でも簡単に使えるでしょう。ちなみに、これらのアプリは基本的に有料です。
- Webブラウザのパスワード保存機能を使う – ChromeやSafari、Edgeといった主要ブラウザにはパスワード管理機能が内蔵されています。サイトにログインする際にパスワードを保存しておけば、次回から自動入力してくれるので便利です。最近のブラウザはセキュリティも強化されており、マスターパスワードやOSログインと連動した暗号化で保護されます。特別なアプリを入れなくても手軽に始められる点で、ITに不慣れな方にはまずブラウザ機能の活用もおすすめです。
- オフラインで一覧管理する(表計算ソフト等) – パスワードを紙やExcelなどに書き留めて管理する方法です。一覧性は高いですが、他人に見られたり盗まれたりしないよう厳重に保管する必要があります。Excelにパスワード付きでファイル暗号化を施せば、一つのマスターパスワードで複数のパスワードを守る形となり、それなりに安全性は確保できます。ただしファイルのバックアップやマスターパスワードの管理には注意が必要です。ちなみに私はこの方法を使ってます。今後1Passwordに移行予定。
- 紙のメモに書く – 最終手段として、パスワードを紙のノート等に書いて物理的に保管する方法もあります。ネット経由で情報漏洩する心配はないため意外に安全との意見もありますが、盗難や紛失、覗き見のリスクがあります。どうしても紙に書く場合は、金庫や鍵付き引き出しに保管する、机上に置きっぱなしにしないなど徹底しましょう。また前述のように、パスワード全文を書くのではなくヒントとなる断片やルールだけを書くなど工夫すると安全性が高まります。
上記の中で、特に安全で便利なのは①と②の方法です。基本的にはパスワード管理アプリやブラウザに任せ、各サービスごとにランダムで強固なパスワードを使うのが最善策でしょう。アプリの場合、「サービス終了したらどうなるの?」と心配になる方も多いと思いますが、たとえサービスが終了する場合も事前に終了予定の告知があるでしょうし、1Passwordの場合はパスワードはすべてローカルに暗号化保存されており、オフラインでも利用可能です。エクスポートしてCSV形式などで全データも出力できます(要マスターパスワード)。なので別のアプリへのデータ移行も可能なので心配する必要はありません。
どうしてもデジタル管理に抵抗がある場合のみ③や④を検討すると良いですが、その際も前述のように十分な対策を取ってください。
補足: マスターパスワードは覚えておこう!
パスワード管理アプリやブラウザを利用する場合でも、「アプリ自体のログイン用パスワード」や「PC・スマホのロック解除パスワード」は最後の砦として自分で覚えておく必要があります。これらはいわば全ての鍵を保管する金庫の鍵に相当します。このマスターパスワード(および主要なメールアカウントやApple/Googleアカウントのパスワードなど)は、ぜひ先述のフレーズ+ルールの方法で強力かつ覚えやすいものを設定しましょう。第三者に知られたり、紙の中だけに書いて本人も忘れてしまったりすると非常に困るため、この部分は頑張って記憶するのがおすすめです。
補足: 二要素認証も有効活用を
パスワード管理とは直接関係しませんが、セキュリティ対策として二要素認証(2FA)も必ず有効にしましょう。対応しているサービスでは、パスワードに加えワンタイムコードや生体認証など第二の認証を要求する設定が可能です。二要素認証を有効化しておけば、たとえパスワードが漏れてしまっても不正ログインを防ぐ強力な抑止力になります。手間は少しかかりますが、特に重要なアカウントではぜひ設定しておいてください。
次世代の認証技術:パスキー(passkey)の活用

最後に、「パスワード自体を使わない」次世代の認証技術にも触れておきましょう。最近AppleやGoogle、Microsoftなど大手各社が相次いで導入を進めている「パスキー(passkey)」と呼ばれる仕組みです。パスキーはFIDOアライアンスとW3Cが策定したパスワードレス認証の一種で、文字通りパスワードを入力せずにログインできるようにする技術です。
パスキーでは、サイトやアプリへのログイン時に従来のパスワード入力の代わりに、デバイスの生体認証やPINを使って本人確認を行います。例えば、対応サービスならスマートフォンの指紋認証や顔認証で「サインイン」できてしまい、複雑なパスワードを覚えたり入力したりする必要がなくなるのです。感覚的にはスマホのロック解除と同じで、「触れるだけ・見るだけ」で安全にログインできる次世代の仕組みと言えます。
「本当にそんな方法で安全なの?」と思うかもしれません。しかしパスキーは裏側で高度な公開鍵暗号技術を用いており、パスワードよりもフィッシングやリスト型攻撃に強い高い安全性を実現しています。サービス側にはパスワード(秘密)は一切置かれず、盗まれる心配がありません。またユーザー側にとっても、推測困難なパスワードを何十個も管理する負担から解放される画期的なメリットがあります 。
パスキーはまだ新しい技術ですが、現在その普及は着実に進んでいます。 Apple・Google・Microsoftの三大プラットフォームがいずれもサポートを表明し、主要ブラウザ(Safari/WebKit、Chrome/Blink、Firefox/Gecko)も対応を進めている状況です。既にGoogleアカウントやMicrosoftアカウント、Apple ID、主要なSNSや一部の金融機関など、対応サービスも少しずつ増加中です。ある調査では「パスキー対応サービスでパスキーを有効にした」ユーザーが69%にのぼるとも報告されており、多くの人が便利さと安全性を実感し始めています。
もっとも、世の中の全てのサービスが一朝一夕にパスキーへ置き換わるわけではありません。完全にパスワードが不要になるまでには数年かかるとも予想されており、当面はパスキーとパスワードが併存する期間が続くでしょう。現時点でもパスキー対応サイトでは「パスワードかパスキーか」を選べたり、初回登録時に従来のパスワードを要求されるケースもあります(セーフティネットとして従来方式を残している状態です )。したがって、今すぐパスワードの管理が不要になるわけではない点には注意が必要です。
とはいえ、パスキーは間違いなく次世代認証の本命です。セキュリティ面でも利便性でもパスワードを大きく上回る技術であり、今後ますます多くのサービスで採用が進むと考えられています。ITに詳しくない方でも、対応サービスで一度使ってみればその便利さを実感できるでしょう。日頃パスワード管理に悩んでいる方は、ぜひ対応している身近なサービスからパスキーを試してみることをおすすめします。例えばGoogleやAppleのアカウント、AmazonやTwitterなど対応が発表されているサービスで設定してみると良いでしょう。設定自体は難しくなく、案内に従って進めれば数分で完了します。以降は次回ログインから指紋や顔認証でスムーズにアクセスできるようになります。
まとめ
パスワードの安全確保は、初心者であっても避けて通れない大切なポイントです。「長く複雑だけど自分は覚えやすい」パスワードを作る工夫 や、パスワード管理ツールの活用 によって、セキュリティと利便性を両立させましょう。
具体的には…
- 安易なパスワードはNG: 名前や誕生日、短い番号列、辞書単語、使い回しなどは避ける 。最低12~15文字以上、英大小字・数字・記号を織り交ぜる 。
- 覚えやすいフレーズを活用: 好きな言葉や歌詞などからローマ字変換+自分ルールで強力なパスワードを作る。意味のある文をベースにすれば覚えやすく、変換により第三者には推測困難。
- ユニークなパスワード: サービスごとに必ず異なるパスワードを使う。自作する場合はサイトごとのキーワードを組み込む、または毎回ランダム生成してパスワード管理アプリに保存する。
- 管理アプリやブラウザを活用: 信頼できるパスワード管理ツールを使えば、人が覚えなくても安全に大量のパスワードを扱える。初心者にはまずブラウザの保存機能や有名な管理アプリの利用が手軽。
- マスターキーはしっかり記憶: 管理ツールの主パスワードや端末のログインパスワードなど「鍵の鍵」は強力かつ忘れないものを設定する(フレーズ活用がおすすめ)。
- 二要素認証の併用: パスワードだけに頼らず、可能な限りワンタイムコードや生体認証を追加してアカウントを守る。
- 新技術も試してみる: パスキー対応サービスでは積極的にパスキーを使ってみましょう。パスワード入力の手間とリスクを減らせ、初心者でも簡単・安全に利用できます。
安全なパスワード管理は最初は少し手間に感じるかもしれません。しかし、一度仕組みを整えてしまえば日々の負担は大幅に減り、何より大切なアカウントを守れる安心感があります。ぜひ本記事の方法を参考に、今日からあなたのパスワード運用を見直してみてください。小さな工夫と最新ツールの活用で、誰でも安全なネット生活を送ることができます。