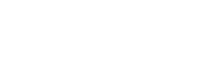当サイトのリンクには一部プロモーションを含みますが、一切その影響は受けず、公正・中立な立場で制作しております。
2018年に発売されたCanon RF 50mm F1.2L USMは、RFマウントの最初のLシリーズプライムレンズとして、多くのキヤノンユーザーに愛されてきました。でも、最近の特許申請から、その後継機「RF 50mm F1.2L USM II」が開発中かもしれないという噂が浮上しています。今回は、この特許の内容を基に、詳しく解説していきます。早速見てみましょう!
特許申請の背景:より先進的な光学設計へ
Canon RF 50mm F1.2L USMは、発売からすでに7年が経過しています。RFマウントの初期Lレンズとして優れた性能を発揮してきましたが、Canonは近年、より先進的な光学設計を追求しています。例えば、後玉をセンサーにより近づけたり、AF速度の向上、サイズや重量の最適化を図ったりと、技術革新が目覚ましいんです。
今回注目されているのは、日本特許公開番号2025-118483の申請です。この特許は、大口径レンズの各種収差を補正し、フォーカスグループの軽量化でAFを高速化することを目指しています。特に、サジタルコマフレア(星像の歪み)の低減がポイントで、天体写真家やポートレート撮影で美しいボケを求めるユーザーにとって嬉しい改善点です。
Canonの特許文書によると、「大口径光学系では各種収差の補正が難しく、フォーカスレンズ群の軽量化で高速AFを実現しつつ、フォーカス時の収差変動を抑えるのが課題」とあります。従来の設計では、フロントグループの移動がAF速度を制限していましたが、この新設計ではそれを克服しようとしているようです。
新しい光学設計の特徴:ユニークなアスフェリカル要素
この特許の面白いところは、10種類もの実施例がすべて50mm F1.2仕様である点。通常、特許ではさまざまな焦点距離を混ぜて紅 herring(偽の情報)を入れることがありますが、ここはすべて50mmに集中。かなり本気度が高いと感じます。
設計図では、2つのアスフェリカル要素(LaとLb)が独特の配置でグループ化されており、これがサジタルコマフレアの補正に役立つそうです。
アスフェリカル要素(非球面レンズ要素)とは、カメラレンズや光学機器に使用されるレンズの一種で、表面が完全な球面ではなく、非球面形状を持つものを指します。この設計は、光学性能を向上させるために重要な役割を果たします。
サジタルコマフレア(Sagittal Coma Flare)とは、カメラレンズの光学収差の一種で、特に点光源(例えば星や光の点)が画面の周辺部で歪んだり、彗星(コマ)の尾のような形状に見えたりする現象を指します。
Canonの過去の特許を振り返っても、このような配置は珍しいんですよ。レンズ全体の長さは約120mmで、現行の108mmより少し長くなりますが、光学性能とAF速度の向上を考えれば、許容範囲内でしょう。
具体的なスペック例(最も現実的な16mmバックフォーカス距離のもの):
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 焦点距離 | 48.50mm |
| F値 | 1.25 |
| 半画角 | 24.04° |
| イメージハイト | 21.64mm |
| 全長 | 120.00mm |
| バックフォーカス距離 | 16.33mm |
この設計では、成形アスフェリカルレンズや大型要素を活用して、収差を徹底的に抑えています。結果として、星空撮影でのシャープネス向上や、周辺部のボケの美しさが期待されます。
日本市場での期待:プロからアマチュアまで
日本のキャノンユーザーの間では、CanonのRFシステムがミラーレスカメラの主流となっており、EOS Rシリーズユーザーにとって50mm f/1.2はポートレートの定番レンズです。新バージョンが登場すれば、AFの高速化で動きのある被写体撮影がしやすくなり、天体や夜景好きのフォトグラファーにもアピールするはず。価格は現行の約30万円前後ですが、後継機はさらにプレミアムになるかも?
ただし、注意点として、これはあくまで特許申請段階の研究です。Canonが実際に製品化するかは未定で、発売まで数年かかる可能性もあります。過去の例を見ても、特許が製品になるケースは半々くらい。ワクワクしながら待つのがベストですね!
まとめ:Canonのイノベーションに注目
Canonは光学技術のフロンティアを切り開き続けています。このRF 50mm F1.2L USM IIの噂は、RFマウントの未来を明るく照らす一筋の光。もし発売されたら、すぐに記事にしたいと思います! 皆さんの意見は? コメントで教えてください。