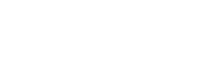当サイトのリンクには一部プロモーションを含みますが、一切その影響は受けず、公正・中立な立場で制作しております。
2025年12月施行の「スマホ新法(スマホソフトウェア競争促進法)」が話題になってます。スマホ新法とは一体なんなのか?初心者向けに解説しています。iPhone・Androidユーザーへの影響、必要な対応、考えられるリスクまで分かりやすくまとめました。
スマホ新法とは何か?(概要と目的)
スマホ新法は、2025年12月に施行される日本の新しい法律で、正式名称を「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(令和6年法律第58号)といいます。簡単に言えば、スマートフォン市場でAppleやGoogleなど一部企業に偏りがちな状況を是正し、より多くの企業が参入できるよう競争環境を整えることが目的です。

現在、日本のスマホ市場はiPhoneのiOSとAndroid(主にGoogle提供)の2つでほとんど占められており、アプリストアや基本機能もそれぞれの企業が厳しく管理しています。政府と公正取引委員会は、この寡占状態がイノベーションや利用者の選択肢を狭めていると考え、公正で自由な競争を促進する新たなルールを設けました。この法律では影響力の大きい事業者を「指定事業者」とし、指定事業者(現時点ではAppleとGoogleが名指しされています)が正当な理由なく自社のプラットフォーム上で他社のビジネスを妨げたり、自社に有利な扱いをすることを禁止しています。違反時には公正取引委員会が是正命令や罰則(課徴金など)を科す仕組みになっています。
このスマホ新法は、欧州連合の「デジタル市場法(DMA)」に影響を受けた動きで、日本版DMAとも位置付けられます。ただし日本の法律独自の考慮点もあり、ユーザーの安全や青少年保護を理由に一定の制限を正当化できる条項が含まれるなど、欧州より柔軟で現実的な運用ができる部分もあります。つまり、公正な競争を促しつつも、セキュリティや利用者保護を損なわないようバランスを取ることが重視されているのが特徴です。
どんなユーザーに影響があるのか?(影響を受ける利用者層やサービス)
iPhoneおよびAndroidユーザー全般に何らかの形で影響がありますが、特に変化を感じる可能性が高いのはiPhoneユーザーでしょう。これまでiPhoneではAppleが運営するApp Store以外からアプリを入手することは基本的にできませんでしたが、スマホ新法のもとではApp Store以外の方法(サードパーティのアプリストアや直接ダウンロード=「サイドローディング」)でアプリをインストールできる可能性が出てきます。その結果、Appleの審査を通らないアプリや、App Storeでは提供されていないアプリも利用できるようになるかもしれません。一方、Androidユーザーは以前からGoogle Play以外にもAmazonや携帯キャリア提供のストア、直接APKファイルを入手する方法などが存在していました。したがってAndroidでは劇的な変化はないかもしれませんが、日本国内でも改めて「利用者が自分で好きなアプリストアや入手先を選べる」というルールが強化され、利用環境がよりオープンになると期待されています。
また、影響を受けるサービスとしては真っ先に公式アプリストア(AppleのApp StoreやGoogle Playストア)が挙げられます。指定事業者であるAppleとGoogleは、今後これらストアの運営方針を見直し、開発者に対して他の決済方法を認めたり、他社ストアの参入を許容したりする必要があります。たとえばアプリ内課金では、これまでAppleは自社の決済システム以外を禁止し手数料(最大30%)を徴収してきましたが、新法施行後は外部の決済システム利用や、アプリ内から外部ウェブページへの誘導(リンク設置)も許可しなければならなくなります。その際、外部決済を選んだ利用者が不利にならないよう、リンクの表示を小さくしたり不当に高い手数料を課したりすることも禁止されます。これらの変更により、ユーザーはアプリ課金の支払い方法についてApple/Google以外の選択肢を得られる可能性が高まります。
さらに、スマートフォンの基本機能や他デバイス連携にも影響があります。スマホ新法は「OSが本来持つ機能やAPIを特定企業だけが独占せず、競合他社にも開放すること」を求めています。例えば現在、ウェブブラウザについてiPhoneでは全てSafariのレンダリングエンジン(WebKit)を使う制限がありますが、新法により他社製ブラウザが独自のエンジンを使用できる可能性があります。検索エンジンや翻訳アプリ、非接触決済アプリ(電子マネー・交通系ICなど)についても、ユーザーが自由にデフォルトのものを選択できるよう求められています。実際、ガイドライン草案を受けてiOS 26やAndroid 16のベータ版では、設定画面でこれら「デフォルトアプリの選択」項目が拡充されつつあります。例えばiPhoneでも、将来的にApple Pay以外の決済アプリを標準の支払いに設定することや、Safari以外を標準ブラウザにすることがより簡単になるかもしれません。
デバイス連携の面でも、Apple製品同士のみで使える機能の開放が議論されています。現在Apple WatchはiPhoneとしか連携できず、通知や決済、ロック解除など多彩な機能連携は「iPhone+Apple Watch」の組み合わせでしか実現しません。しかし他社製スマートウォッチとiPhoneの組み合わせでは利用できない機能があるのは参入障壁とみなされ、新法のテーマである「障壁の排除」により改善が求められています。つまり、今後は「iPhone+他社製スマートウォッチ」でもロック解除や決済連携が可能になる、公正なデバイス間相互運用性の実現が期待されます。同様に、AirPodsと他社スマホとの高度な連携など、特定メーカーの組み合わせに限定されていた機能が広く開放される可能性があります。これはユーザーにとって、特定メーカーの縛りなく自由に周辺機器を選べるメリットとなるでしょう。
以上のように、スマホ新法は一般のスマホ利用者全員に関係する変化ではありますが、実際の影響度合いは利用者ごとに異なります。普段から公式のApp Store/Playストアのみでアプリを入手し、決済も標準方法しか使っていないという方は、新法が施行されても当面は大きな変化を感じない可能性があります。一方、スマホの使いこなしに積極的で「もっといろいろなアプリやサービスを試したい」「好きな決済手段を使いたい」と考えるユーザーにとっては、新法により選択肢が増える恩恵を受ける場面が増えるでしょう。特にiPhoneユーザーは、今後リリースされるiOSのアップデートで新しい設定項目や選択肢が提示される可能性があります。その際、自分のニーズに合わせて設定を変えることでより便利に使える反面、従来より注意深く安全性を確認する姿勢も求められるかもしれません。
対象者は何をすれば良いのか?(対応策・心構え)
スマホ新法の施行によって利用環境が変わるとしても、ユーザー側で今すぐ大きな行動を取る必要はありません。基本的なスタンスとしては、「新しい選択肢が増えるが、使うかどうかは自分次第」という心構えでいると良いでしょう。以下に、iPhone/Androidユーザーが新法に備えてできる具体的な対応策やポイントをまとめます。

- OSやアプリを最新バージョンにアップデートする: 新法への対応は各スマホOSのアップデートとして提供される見込みです。最新のiOSやAndroidに更新することで、法律に沿った新機能(例: デフォルトアプリ選択の拡充やセキュリティ対策)が自動的に反映されます。常にアップデートを適用し、公式の変更情報に目を通す習慣をつけましょう。
- 不要なサイドローディングは避ける(初期設定を維持する): iPhoneでもAndroidでも、公式ストア以外からアプリを入れる設定(「不明なデベロッパーからのインストールを許可」等)は、初期状態では無効(許可しない)になっています。特にこだわりがない限り、この設定は変更せず維持することをおすすめします。新法が施行されても、設定を自分でオンにしない限り勝手に外部ストアのアプリが入ることはありません。興味本位で出所不明のアプリをインストールしないことが最大の防御策です。どうしても必要な場合だけ有効化し、用が済んだらオフに戻すくらい慎重でも良いでしょう。
- 信頼できる配布元からのみアプリを入手する: 今後、AppleやGoogle以外からアプリを入手できる場面が増える可能性がありますが、その場合は提供元(配信元の企業やサイト)をよく確認してください 。例えば、大手企業や公式に認められたストアであれば比較的安心ですが、聞いたことのないようなサイトやSNS上で配布されるAPK/プロファイルはインストールしない方が無難です。公式ストア以外から入れるアプリは自己責任となることを忘れずに、評判や安全性の情報を事前に調べましょう。
- セキュリティ対策ソフトや機能の活用: AndroidではGoogle Playプロテクトなどデバイス内蔵のセキュリティ機能がありますので有効にしておきましょう。iPhoneでも、今後サイドローディングが解禁された場合に備えて不審な挙動を検知する仕組みが用意される可能性があります(たとえばインストール時の警告表示や、エンタープライズ用のモバイル管理(MDM)アプリの活用など)。必要に応じて信頼できるセキュリティアプリを導入し、端末をスキャンすることも検討してください。
- お子様がいる場合の設定確認: スマホ新法によっては、フィルタリングやペアレンタルコントロールの設定も見直す必要が出てくるかもしれません。現状iPhoneでは全ブラウザがWebKitエンジンを使うためフィルタリングが効きやすいですが、将来他社エンジンのブラウザアプリが出るとフィルタリングが機能しないリスクがあります。そのため、保護者の方はOSアップデート後に設定アプリのペアレンタル制限項目を確認し、新たに許可/禁止できる項目が増えていないかチェックしましょう。場合によっては、18歳未満の端末では外部ストアからのインストールを禁止する設定を利用することも検討すべきです。
- 最新情報をフォローする: 法律の具体的な運用(ガイドライン)や各社の対応策は、今後もアップデートされます。公正取引委員会や総務省、経済産業省などの公式発表、ニュースリリースに目を通すようにしましょう。例えば公正取引委員会の特設ページや経済産業省のガイドライン解説サイトでは、新法の概要やQ&Aが公開されています(パブリックコメント結果も含め順次更新)。それらをブックマークし、月に一度でも確認する習慣をつけておくと安心です 。また、AppleやGoogleからユーザー向けに告知が出ることも考えられるので、公式ブログやサポート情報にも注意しましょう。
以上の対応策を念頭に置いておけば、スマホ新法が施行された後も大きく困ることなく、新しい環境に順応できるはずです。「便利になるかもしれないが、安全第一」という姿勢で臨み、焦らず必要な範囲で新機能や選択肢を活用するようにしましょう。
考えられるリスクと注意点(セキュリティ・詐欺アプリ・サポート対応の変化など)
スマホ新法はユーザーに選択肢拡大という恩恵をもたらす反面、いくつか注意すべきリスクも指摘されています。最後に、想定される主なリスクと対策ポイントを整理します。
- セキュリティリスクの増大: 最大の懸念は、悪意のあるアプリが流通しやすくなる可能性です。AppleがこれまでApp Storeの厳格な審査で排除してきたようなマルウェア(ウイルス感染アプリ)やスパイウェア、個人情報を騙し取るフィッシング詐欺アプリが、外部経由でインストールされてしまうリスクがあります。公式ストアという「柵」が低くなる分、ユーザー自身がアプリの安全性を見極める必要性が高まるでしょう。対策としては前述のように未知の提供元からインストールしないことが第一です。また、OS提供側でも「ガードレール」として、外部ストア経由アプリには通常より厳しい権限制限をかける、インストール時に警告や確認プロンプトを表示する、問題があれば遠隔で利用停止にできる仕組みを設けるなどの措置が検討されています。こうした機能も活用し、常に「このアプリは安全だろうか?」と意識する習慣をつけましょう。
- 詐欺アプリ・偽ストアへの注意: 新法施行前後には、「〇〇法対応!おすすめ新ストアはこちら」「無料で高機能なアプリを直接ダウンロード!」といった宣伝がインターネット上に出回る可能性があります。中には巧みに公式風のサイトを装った偽のアプリストアや、有名アプリを装った偽物アプリも登場し得ます。実際、欧州DMA施行時にもユーザーの関心を悪用したフィッシング詐欺が報告されています(「新しいApp Store」を騙るメール等)。日本でも同様の手口が考えられるため、安易にリンクをクリックしない、アプリの公式サイトや正式リリース情報を確認する、といった慎重さが求められます。公式に認められていないストアアプリをインストールしようとすると端末が警告を出す場合もありますので、そのような警告は無視せず対応してください。
- サポート対応・保証範囲の変化: AppleやGoogleのサポート体制にも変化が生じる可能性があります。例えばiPhoneで外部から入れたアプリが原因で不具合が起きた場合、従来であれば「Appleが審査したApp Store配信のアプリ」に限ってサポートしていたところ、今後は「非公式経路で入れたアプリについてはサポート対象外」となることも考えられます。実際、Macの世界ではGatekeeperを無効化して入れたソフトによる問題は自己責任でしたが、モバイルでも似た扱いになる可能性があります。メーカー保証(修理や交換)についても、非公認ソフトウェアが原因の故障・障害は保証適用外となるリスクがあります。ユーザー側でできる対策は、問題発生時に備えてデータのバックアップをこまめに取っておくことと、不審な挙動があれば早めにアンインストールや初期化を行うことです。また、どのアプリストア経由で入手したかを把握しておき、不具合時に適切な窓口(公式ストアか、外部ストアの運営元か)に問い合わせできるように情報を整理しておきましょう。
- 青少年や弱者の保護策: 前述のように、外部アプリの解禁によってスマホのフィルタリングが効きづらくなる懸念があります。違法・有害情報へのアクセスを防ぐ仕組みが破られやすくなれば、青少年を守る観点で問題です。政府もこの点は認識しており、新法の運用ガイドラインには例外規定として「セキュリティ確保や青少年保護のために必要な場合、プラットフォーム事業者が一定の制限措置を取ること」が許容されています。例えば、違法なオンラインカジノアプリの配布を防ぐためにストア上で削除・禁止したり、アプリ内の課金ページ遷移時に警告画面を出すことなどは正当化される見込みです。保護者の立場では、新法施行後もしばらくは子どもの利用するスマホは従来通り公式ストア経由の利用に限定させるなど、安全が確認できるまで慎重に運用することも検討してください。また政府や教育機関からフィルタリング回避への対策情報が発信される可能性がありますので注視しましょう。
- 利用者への影響は徐々に現れる: 最後に留意したいのは、スマホ新法が施行されたからといって即座に日常が激変するわけではないという点です 。ルール上は2025年末以降すぐに適用となりますが、実際にはAppleやGoogleが具体的措置を講じ、それがユーザー体験に反映されるまでには段階的な移行期間があるでしょう。したがって、「気づいたら便利な機能が増えていた」程度の緩やかな変化に留まる可能性も高いです。その一方で、法施行直後は不確実性もあるため、最新の公式情報に注意を払い、怪しい情報に惑わされないようにしてください。法律の趣旨はあくまで利用者の利益向上にありますが、最終的に自分の身を守るのは自分です。新たな選択肢を賢く活用しつつ、基本的な安全対策を怠らないようにしましょう 。
まとめ
スマホ新法(スマホソフトウェア競争促進法)は、私たちのスマートフォン利用にこれから徐々に影響を与えていく重要なルールです。iPhone・Androidユーザーともに、自分の使い方に応じて新しいメリットを享受できる一方、自己防衛の意識もこれまで以上に求められます。公正な競争によって生まれる便利なサービスを取り入れつつ、セキュリティとプライバシーを守ることを忘れずに、豊かなスマホライフを送りましょう。