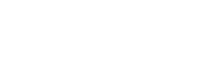当サイトのリンクには一部プロモーションを含みますが、一切その影響は受けず、公正・中立な立場で制作しております。
2025年6月6日未明、日本の宇宙スタートアップispace(アイスペース)が自社開発した月面着陸船による再挑戦のミッションに臨みます。ispaceは2023年4月に初めて月面着陸を試みたものの惜しくも失敗に終わりましたが、その経験を踏まえ技術と計画を改良し、再び月面への軟着陸を目指しています。この記事では、ispace社の概要と創業背景、ビジネスモデル、これまでの歩みから、今回の月面着陸ミッション(Mission 2)の詳細、そして過去のミッション(特に初号機HAKUTO-R Mission 1)の結果と意義について解説します。また、他国・他企業の月面着陸との比較や、宇宙ビジネス全体のトレンドと日本の立ち位置、さらに宇宙開発・宇宙ビジネスが人類にもたらす意義と今後の展望についても、一般の読者向けにわかりやすく紹介します。結果を含む最新の情報はこちらの記事にまとめています。
ispace社とは?企業概要とこれまでの歩み
ispace株式会社は2010年に創業された日本発の宇宙スタートアップ企業で、Googleが主催した月面無人探査レース「Google Lunar XPRIZE」に参加した日本チーム「HAKUTO(月兔)」を母体として誕生しました。Google Lunar XPRIZEは、各国の民間チームが月面への無人軟着陸と500mの走行を競った国際レース(2007~2018年)でしたが、残念ながら優勝チームは出ずに終了しています。しかしispaceは大会終了後も月面探査を続けることを決断し、当時ファイナリストとして得た知名度や技術をもとに約9,000万ドル(約100億円超)の資金調達に成功、自社の月着陸船と探査ローバーの開発を加速させました。創業者でCEOの袴田武史氏は「人類の生活圏を宇宙に広げ、持続性のある世界へ」(“Expand our planet. Expand our future.”)というビジョンを掲げており、月面資源の開発や月と地球を一体とした経済圏(月面経済圏)の創出を目指しています。
ispaceのビジネスモデルは、大きく分けて「ペイロード(貨物)輸送サービス」「データサービス」「パートナーシップ提供」の3つから構成されています。中でも中核となるペイロード輸送サービスでは、顧客企業や宇宙機関の荷物(実験装置やロボットなど)をispaceの開発した小型月着陸船(ランダー)や月面探査車(ローバー)に搭載し、月面まで届けることを事業の柱としています。例えばispaceの初号機ミッション(後述の「HAKUTO-R Mission 1」)では、UAE(アラブ首長国連邦)の月面探査ローバーやJAXA(宇宙航空研究開発機構)・民間企業が共同開発した超小型ロボットなど、国内外の複数のペイロード(搭載貨物)を月に輸送する計画でした。このようにランダー開発と輸送サービスで収益を上げつつ、将来的には月面で収集した資源や探査データを販売するデータサービス事業にも注力する方針です。ispaceは2023年4月に東京証券取引所グロース市場に新規上場を果たしており、日本の宇宙ベンチャーとして初の上場企業となりました。これまでに累計で約268億円(約2億ドル)以上の資金を調達しており、現在は東京を本社にルクセンブルクや米国にも拠点を置き、世界で約300名の社員を擁するグローバル企業へと成長しています。
再挑戦となる月面着陸ミッション「HAKUTO-R Mission 2」の概要

ispaceが挑む今回のミッションは「HAKUTO-R Mission 2」と呼ばれ、2025年1月15日に打ち上げられた2号機の月着陸船「RESILIENCE(レジリエンス)」による月面着陸ミッションです。ミッション名には、大手銀行である三井住友銀行(SMBC)がパートナーとして冠名に含まれており、「SMBC x HAKUTO-R Venture Moon」とも称されています。RESILIENCEランダーは低エネルギー軌道を用いて約4か月半かけ月への航行を続け、2025年5月上旬に月周回軌道への投入(ローナー軌道への遷移)に成功しました。そして着陸予定日として2025年6月6日(日本時間)をターゲットに定め、午前4時24分(JST)頃に月面への降下を試みる計画です。万が一当日の状況が不安定な場合に備え、6月6日~8日の間で計3か所のバックアップ着陸候補地と予備日程も設定されています。着陸を行う予定の地点は月面北部の広い平原「氷の海(Mare Frigoris)」付近で、6日未明の降下ではまず午前3時15分頃(JST)に高度約100kmの周回軌道からランダーが離脱しエンジン噴射を開始、その約1時間後に目標地点付近への軟着陸を目指す流れです。
着陸船RESILIENCEには、いくつかの重要なミッション目的・搭載機器があります。最大の目玉は、ispaceが自社開発した超小型月面探査車「TENACIOUS(テナシアス)」の展開です。TENACIOUSローバーは重量わずか数kg程度の小型ロボットですが、月面走行を行いながらレゴリス(土壌)採取の技術実証を行うことがミッション2の目的の一つとなっています。月面の砂や土を掘削・採取し分析することは、将来の資源開発(例えば水や鉱物の利用)に不可欠な技術であり、民間企業によるレゴリス採取の試みは世界的にも注目されています。また、本ミッションでは国連教育科学文化機関(UNESCO)との協力により、世界275の言語で書かれた文言や文化的記録を収めた「メモリーディスク」が搭載されました。このディスクは「万が一地球上で人類文明が危機に瀕した場合でも、人類の文化の一部を月面に残し未来へ伝える」というコンセプトで作られたタイムカプセル的な試みであり、国際的な意義を持つ搭載物です。
打ち上げと着陸の方法についても触れておきましょう。RESILIENCEランダーは2025年1月に米フロリダから打ち上げられましたが、前回Mission 1と同様にSpaceX社のファルコン9ロケットが使用されました(Mission 1では2022年12月にFalcon 9で打ち上げ)。着陸シーケンスは完全自律制御で行われ、ランダー搭載のカメラやレーザー高度計、推進装置などが連動して減速降下します。ispaceによれば、Mission 2ではMission 1の教訓を反映し制御精度を高めているとのことで、これまで宇宙空間で行った軌道制御マヌーバ(軌道変更エンジン噴射)は全て計画通り遂行され、ランダーの主要7サブシステムも全て正常に動作しています。着陸直前には高度計やカメラで地形を認識しながら減速し、時速数千kmから0kmまで一気に緩めて月面に降り立つ必要があります。月には大気が無いためパラシュートなどは使えず、全てロケットエンジンの逆噴射で減速する必要があります。この月の重力圏下でのエンジン降下制御は技術的に非常に難しく、わずかなセンサーの誤差や推進剤残量の計算ミスが致命的な影響を及ぼし得るため、ミッションの「成否を分ける最終関門」と言えるでしょう。ispaceの袴田CEOは「信頼性の高いスラスター(推進機)や実績あるナビゲーション技術を用い、高い確率で着陸できるよう設計してきた。全ての機器がしっかり動作しており、十分に着陸できる可能性がある」と自信を示しています。一方で「ミッション前半で全機器チェックを行い万全を期しているが失敗リスクの低減にも最大限努めてきた」と述べ、万一の不測事態に備えた並行開発や資金計画についても言及しています。総合的に見て、前回より成功の公算は高まっているものの、最後まで気を抜かず慎重な運用が求められると言えるでしょう。
初号機「HAKUTO-R Mission 1」の挑戦と教訓
今回のMission 2に先立ち、ispaceは「HAKUTO-R Mission 1」で日本企業初となる月面着陸への挑戦を行いました。Mission 1の月着陸船(ランダー)は2022年12月11日にSpaceX社のFalcon 9ロケットで打ち上げられ、約4か月半かけて2023年3月に月周回軌道へ投入されました。その後、2023年4月25日に月面着陸を試みましたが、降下の最終局面で通信が途絶し、軟着陸は達成できませんでした。ispaceの解析によれば、着陸直前に高度計のデータ不整合が生じたことなどから機体が推進剤を予想以上に消費し、最後は燃料枯渇によって減速が不十分なまま月面に激突した可能性が高いとされています(着陸船の残骸と見られるものも月面上で確認されています)。Mission 1では、UAEの月面ローバー「ラシド」やJAXAとタカラトミー・ソニーが開発した超小型変形ロボット、民間企業による実験装置など多数のペイロードが搭載されていました。これらは着陸失敗により目的を果たせませんでしたが、Mission 1自体は10段階中8つのマイルストーン達成に成功し(月到達や月周回投入までを達成)、日本の民間企業として世界でも例のない実績を残しました。
Mission 1の意義は、単に「成功まであと一歩だった」ことだけでなく、その経験が確実に次のMission 2へと受け継がれている点にあります。実際、Mission 1で得られたデータや教訓を活かし、ispaceのエンジニアチームは航法誘導制御(GNC)の精度向上やセンサー類の改良を行いました。例えば降下時の高度推定アルゴリズムの見直しや、推進系バルブ制御の改良、ソフトウェアの冗長化など、多面的な改善が図られています。また資金面でも、Mission 1の前からMission 2・3の開発資金を並行して確保しておくというビジネス戦略を取り(従来は1ミッション毎に資金調達→開発という流れでしたが、それでは失敗時に次が続かないリスクがあるため)、Mission 1の失敗が即会社の存続危機とならないようリスク分散がなされていました。袴田CEOはMission 1後の会見で「直ちに学びをMission 2と3へ活かせる体制ができている」と語っており、まさに今回のMission 2はその言葉を証明する再挑戦と言えるでしょう。初号機の挑戦は惜しくも未完となりましたが、日本発の民間月面探査として歴史的快挙に挑んだ意義は大きく、海外メディアからも「民間による月面軟着陸への新たな一歩」として大きく報じられました。Mission 1の経験で培われた知見は、ispaceのみならず今後の世界の月探査ミッション全体にも貴重な財産となっています。
世界の月面着陸レース:他国・他企業との比較
ispaceの挑戦は、日本だけでなく世界の月面探査における新たな潮流の一部です。これまで月面への軟着陸を成功させたのは、アメリカ(NASAのアポロ計画や無人探査機)、旧ソ連(ルナ計画)、そして近年では中国(嫦娥計画)やインド(チャンドラヤーン計画)といった国家機関が中心でした。民間主体での月面着陸は長らく実現していませんでしたが、2019年にイスラエルの非営利団体SpaceILが試みた「ベレシート(創世記)」(政府支援を受けた民間チームによる)を皮切りに、徐々に世界各地の企業が挑戦を始めています。ispaceのMission 1(2023年4月着陸試行)は民間による挑戦としては世界で2番目、日本初のケースでした。残念ながらSpaceIL機もispace機も着陸は成功しませんでしたが、その後、米国のIntuitive Machines社が開発した無人月着陸船「Nova-C(IM-1ミッション)」が2024年2月に月面への軟着陸に成功し、民間企業初の月面ソフトランディングを達成しました。Nova-C(愛称「オデッセウス」)は着陸時にやや機体が傾くトラブルはあったものの機能を維持し、約11日間にわたり月面で観測機器を稼働させています。一方、同じくNASAのCLPSプログラムに参加する米アストロボティック社の着陸船「ペレグリン」は、2024年1月に新型ロケット(ULA社のヴァルカン)で打ち上げられましたが、投入後に推進剤漏れ事故が発生してミッション続行不能となり、月面到達前に失敗しました。そのほか、Intuitive Machinesは2025年3月にも2機目の着陸船(Nova-C IM-2ミッション)を月の南極付近に降下させましたが、こちらは着地後に機体が横倒しになるトラブルが発生し、完全な成功には至っていません。
ではispaceの位置付けはどうでしょうか。他社と比較すると、ispaceのランダーはペイロード100kg未満級の小型ランダーである点が特徴です。小型ゆえに運搬できる荷物量は限られますが、その反面打ち上げコストが低く、また単独機で柔軟に打ち上げ・着陸時期や場所を選定できるメリットがあります。大型の着陸船は一度に多くの荷物を運べる反面、他のペイロードとの相乗り調整が必要でスケジュールや着陸地点の自由度が制約されますが、小型で高頻度に飛ばせるランダーならニーズに応じたタイミング・場所にピンポイントで届けられる利点があります。この戦略は「月面版デリバリーサービス」とも言えるもので、ispaceは将来的に年数回程度の定期便的な月面輸送サービスを目指しています。一方、米国ではスペースX社が開発中の超大型宇宙船「スターシップ」をNASAアルテミス計画の有人月着陸船に提供するなど、規模の大きい月開発計画も進んでいます。スペースXはロケット分野での低コスト化で月探査にも間接的に貢献しており、実際ispaceのミッションも同社の安価な打ち上げサービスを活用しています。さらに2025年以降にはブルーオリジン社(米国)の大型月面着陸船「ブルームーン」や、各国の企業・宇宙機関による月探査ミッションが相次ぐ予定で、まさに「月面着陸元年」から「月面商用化時代」へ移行しつつあるといえるでしょう。
宇宙ビジネスの潮流と日本の立ち位置
近年、宇宙ビジネスは世界的に“New Space”と呼ばれる新興企業主体の潮流が加速しています。ロケット打ち上げの民間開放や低コスト化、人工衛星データ利用の拡大、そして月・火星といった深宇宙探査への商業企業の参入など、かつて政府機関の独壇場だった宇宙開発にベンチャー企業の革新的なサービスが続々と登場しています。特に月面は、NASAのアルテミス計画による有人月探査復活の動きに呼応して、新興企業にとっても大きなビジネスチャンスとなっています。NASAはCLPS(商業月面ペイロードサービス)というプログラムで民間に月探査をアウトソースし、前述のIntuitive Machines社やアストロボティック社など複数企業と契約を結んで科学機器の輸送を委託しています。ヨーロッパでも欧州宇宙機関(ESA)が月資源採掘やインフラ構築に関心を示し、2025年にはispace欧州法人がESAの小型月探査ミッション支援に契約するなど協業の動きも出ています。このように「月面市場」は国際的に立ち上がりつつあり、月面着陸船やローバーの開発・打ち上げ・運用をビジネスとして成立させようとする試みが各国で進んでいます。
その中で日本の立ち位置を見ると、官民それぞれユニークな役割を担っています。官(政府・宇宙機関)では、JAXAが2023年に小型着陸実証機「SLIM(スリム)」を打ち上げ、2024年1月に日本初となる月面着陸を成功させました。SLIMは着陸精度100m以内という高い技術目標に挑みましたが、降下中に一部エンジン故障が発生し不安定な姿勢で着地するトラブルを経験しました。それでも機体は健在で、着陸直後にデータ取得と画像送信に成功、その後一時休眠状態に陥りながらも月の夜明けで太陽電池が復活し再起動するというドラマも見せています。SLIMの成功で日本は世界で4か国目となる月面着陸成功国となり、着陸精度や小型探査の技術で高い実力を示しました。一方、民間ではispaceが筆頭株であり、他にも人工流れ星のALE社や小型衛星メーカーのアクセルスペース社、宇宙旅行事業に乗り出すIHI・Space BDなど、多彩なベンチャーが台頭しています。小型ロケット開発ではインターステラテクノロジズ社が何度も打ち上げ実験を行い、一部成功も収めています。日本政府も宇宙基本計画で民間活用を掲げ、資金面・制度面でベンチャーを後押しする動きを強めています。ispaceのような民間企業の成功は、日本の宇宙開発力を示す象徴となり得るため、国内の期待値も高まっています。
総じて、日本は官民連携で「月面ビジネスの開拓」に挑んでいる状況と言えます。政府主導の高精度技術実証と、民間主導のビジネス創出が車の両輪となり、国際的な月開発レースの中で存在感を示しつつあります。
宇宙開発が人類にもたらす意義と今後の展望

最後に、こうした月面開発や宇宙ビジネス全般が人類にもたらす意義について考えてみましょう。宇宙開発というと一見「ロマン」や「夢物語」に感じられるかもしれませんが、その成果は確実に私たちの生活や未来に影響を与えます。
第一に、宇宙開発は科学技術の飛躍的進歩を促します。月面着陸のような高難度ミッションを達成するために開発された新技術や製品(高性能なセンサー、軽量素材、AIによる自律制御など)は、地上の産業や私たちの日常にも応用されます。また、過酷な宇宙環境で使える機器は耐久性や省エネ性能が高く、それらが地球上の災害対応やエネルギー問題解決に役立つ可能性もあります。
第二に、宇宙ビジネスは経済圏の拡大と新市場の創出を意味します。月面に水資源が豊富に存在すれば、それを電気分解して水素・酸素を生成し宇宙用燃料にすることで、月や宇宙空間での経済活動が自律的に回るようになるかもしれません。ispaceが描く将来像「Moon Valley 2040」では、月面で採掘した水から燃料を作り、ロケットを再補給してさらに遠方へ飛ばす、そんな循環型の宇宙経済の姿が示されています。もし月で燃料補給ができれば、火星などさらに遠い惑星探査へのハードルも下がり、人類の活動圏は飛躍的に広がるでしょう。月面には他にもレアメタルやヘリウム3といった貴重資源の存在が期待されており、これらを持ち帰って地球の産業に役立てることも将来は現実になるかもしれません。
第三に、宇宙開発は人類の存続と発展に対する保険となります。地球上の人口増加や環境問題、資源の有限性を考えると、将来の人類が地球以外の拠点を持つ意義は大きいと指摘されています。月や火星に基地や居住地を築くことは、万一地球に大災害や資源枯渇が起きた際のバックアップになるだけでなく、純粋に新たなフロンティアを切り拓くことで社会に活力と希望を与えます。ispaceがUNESCOと組んで月面に「人類の文化の種」を託そうとした試み も、長い目で見れば人類の遺産を宇宙に保存し未来へ繋ぐ一助と言えるでしょう。宇宙から見た地球は青く美しい孤星ですが、その有限性ゆえに、私たちは宇宙へ出ていくことで初めて地球の大切さにも気付かされます。宇宙に挑むことは、人類自身を客観視し謙虚にする精神的な意義も持っています。
今後数十年で、月面には国際的な有人基地が建設される可能性が高まっています。NASAと各国は月周回拠点ゲートウェイを計画し、日本人宇宙飛行士もアルテミス計画で月に立つことが合意されています。その頃には月面に民間企業のロゴを付けた探査車が走り回り、月資源を採掘する重機が稼働しているかもしれません。ispaceは「月面に持続可能な経済圏を築く」という野心的な目標を掲げていますが、決して荒唐無稽な夢物語ではなく、既に世界中で同じ夢を追う仲間たちと競争し協力し合いながら一歩ずつ前進しています。
2025年6月6日早朝、ispaceの小さなランダーが見事月面に軟着陸し、自らの名の通り「レジリエンス(復元力・不屈)」を体現する瞬間を、私たちは固唾を飲んで見守ることになるでしょう。月面から届く一報は、日本の宇宙開発史に新たな1ページを刻むとともに、世界の人々に宇宙への夢と希望をもう一度思い起こさせてくれるに違いありません。人類のフロンティアである月に挑むispaceの壮大な挑戦は、始まったばかりです。そしてその挑戦は、私たちの未来を拓く大きな一歩となるでしょう。
出典:月面着陸ミッションに関するispace公式発表およびプレスリリース、ispace創業者・袴田氏の発言、Google Lunar XPRIZE公式記事、NASA・各社のミッション報告 などを参照しました。