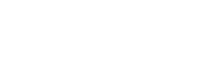当サイトのリンクには一部プロモーションを含みますが、一切その影響は受けず、公正・中立な立場で制作しております。
自動車メーカーのホンダが、なんとロケットの垂直離着陸実験に成功しました!普段は車やバイクを作っているホンダがロケット開発?と聞いて驚く方も多いでしょう。この実験は、ロケットを打ち上げた後に自力で垂直着陸させるというものです。今回は、この挑戦が始まった背景や実験の内容、「再使用型ロケット」とは何なのか、そしてホンダの成果がどれほどすごいのか、今後の展望までを一般の大人にも分かりやすく解説します。専門知識がなくても大丈夫ですので、ホンダの宇宙への挑戦について一緒に見ていきましょう。
なぜホンダがロケット開発に挑むのか
ホンダがロケット研究に乗り出したのは、実は若手エンジニアたちの「自社の技術でロケットを作りたい」という夢がきっかけでした。ホンダは長年の製品開発で培ったエンジンの燃焼技術や制御技術という強みを持っており、それをロケットにも応用できると考えたのです。2019年頃から本格的に低コスト化と利便性向上を目指して再使用型ロケットの研究開発と実験に着手し、「宇宙」という新たな領域で自社技術を活かす挑戦を始めました。
もう一つの背景には、今後の人工衛星ニーズの高まりがあります。私たちの生活ではデータ利用が爆発的に増えており、地球観測や通信などで人工衛星の役割がますます重要になるとホンダは見ています。例えば、地球環境を監視する衛星や、車のコネクテッドサービスに使う通信衛星など、今後多様な人工衛星の需要が拡大すると予測されます。人工衛星を打ち上げる手段であるロケットももっと安く便利にできないか? そこでホンダは、自社技術を活かした再使用型ロケットならばサステナブル(持続可能)な宇宙輸送に貢献できると考え、新領域への一歩を踏み出したのです。
こうしたビジョンのもと、ホンダは着実に準備を進めてきました。北海道の大樹町に専用の実験施設を構え、2024年からエンジン燃焼試験や高度約5mでのホバリング(空中で静止)試験などを重ねてきました 。地道なテストを積み重ねてロケットの挙動を確かめ、安全対策も講じながら技術を蓄えてきたのです。そして満を持して挑んだのが、今回の本格的な垂直離着陸実験でした。
垂直離着陸の実験、いつどこでどう成功?

ホンダ初のロケット離着陸実験が行われたのは2025年6月17日午後4時15分、場所は北海道広尾郡大樹町にあるホンダの専用実験施設です。この実験では、ロケットを打ち上げてから再び垂直に着陸させることに世界へ向けた第一歩として挑みました。目的は、ロケットを再使用するために必要な「上昇・下降時の機体安定制御」と「着地の精密制御」といった要素技術の実証にあります。ロケットは自律制御(自動操縦)によって垂直に上昇し、最高到達高度約271mに達した後、エンジン出力を調整しながら降下。そして発射地点からわずか37cmのずれというほぼピンポイントの位置に着地することに成功しました。飛行時間は56.6秒間で、その間の上昇・下降中のデータも無事取得でき、ホンダが目標としていた離着陸動作の実証は見事に達成されたのです。

この実験に使用されたロケット実験機は全長約6.3m、直径わずか85cmほどの細身の小型機体です。高さ6m強というと、大人の身長の3~4人分か、二階建ての家くらいの高さしかない小さなロケットです。それでも、この“小柄”なロケットが自分でバランスを取りながら空高く舞い上がり、ほぼ同じ場所に真っ直ぐ降りてくることができました。写真や映像で見ると、まるでSF映画のワンシーンのような光景ですよね。ホンダはこの小さな実験機を使って、「ロケットを垂直に着陸させる」という高度な離れ業を日本の民間企業として初めて成功させたことになります。
画像出典:HONDA 再使用型ロケット実験機の離着陸実験に成功
再使用型ロケットって何? どんなメリットがある?
ではそもそも「再使用型ロケット」とは何でしょうか?簡単に言えば、一度打ち上げたロケットを回収してもう一度使えるようにしたものです。通常のロケットは打ち上げのたびに使い捨てられ、燃焼し尽くしたブースター(推進部分)は海に落ちたり大気圏で燃え尽きたりします。極端に言えば、飛行機を1回飛ばすごとに機体を廃棄しているようなもので、とても非効率です。そこで登場したのが再使用型ロケットです。ロケットを垂直に着陸させて壊れないよう回収し、整備してまた打ち上げることで、ロケットを繰り返し運用できるようにするのです。これはロケット界の常識を変える発想で、実現には高度な制御技術が必要ですが、成功すれば宇宙開発のコスト構造を大きく変えます。
再使用型ロケットには具体的に次のようなメリットがあります。
- コスト削減: ロケットを何度も使い回せれば、毎回新造する必要がなくなるため、打ち上げコストを大幅に削減できます。1回使ったら捨てる従来型と比べ、1機のロケットで複数回の打ち上げができれば、その分1回あたり費用が安くなるわけです。
- 高頻度の打ち上げ: 繰り返し使えることで、ロケットの打ち上げ頻度を高めることも期待できます。新しいロケットを一から作る手間が省けるので、短い間隔で次々と衛星を打ち上げることも可能になります。まさに飛行機が毎日飛んでいるように、ロケットも使いまわせれば“定期便”のような感覚で運用できるかもしれません。
- 環境・資源への配慮: 毎回ロケットを廃棄するのは資源の浪費にもつながりますが、再使用型なら部品の廃棄を減らせます。使用済みロケットが海洋投棄される量も減り、持続可能な宇宙輸送に寄与します。地球や宇宙空間の環境負荷を抑える上でも意義があるといえるでしょう。
実際、アメリカのSpaceX(スペースX)社では再使用型ロケットを活用することで打ち上げコストを半分以下に抑えることに成功しています。このように、ロケットを再使用できれば費用も頻度も格段に改善されるため、世界中で研究が進められているのです。
ホンダの成功はどれくらいすごい? 他社との比較
今回のホンダの成果は、日本において画期的な一歩と言えます。冒頭でも触れたとおり、日本の民間企業がロケットの垂直離着陸に成功したのは史上初めてのことでした。従来、日本のロケット開発は宇宙航空研究開発機構(JAXA)や三菱重工などによる大型使い捨てロケット(H-IIAやH3ロケットなど)が中心で、打ち上げ後に回収・再利用する例はありませんでした。実は過去にJAXA(当時のNASDA/ISAS)が垂直離着陸型の小型実験機(RVT)を開発し、2003年には高度42mまで上昇して着陸する実験を成功させたことがあります。しかしこれは研究段階の試みに留まり、実用化には至らなかったのです。ホンダの今回の実験高度271mという記録は、この過去の国内実験を大きく上回るものであり、日本のロケット再利用技術の歴史において飛躍的な前進といえます。
一方、世界に目を向けると再使用型ロケットの先駆者はアメリカのSpaceX社です。SpaceXはFalcon 9(ファルコン9)ロケットで大型衛星を軌道に送り届けた後、ブースター(第1段)を地上や洋上船に垂直着陸させて回収・再利用することを実用化し、世界の度肝を抜きました。2015年に初めてブースターの垂直着陸に成功して以来、何十回と着陸と再打ち上げを繰り返しており、ロケット再使用の実績では他を圧倒しています。ホンダの実験機は全長6m程度とFalcon 9(全長70m超)に比べればずっと小型で、到達高度も300m足らずですから、技術のスケールとしてはまだ比較にならないかもしれません。しかし、基本原理は「垂直に降りてきて着陸させる」という点で共通しており、ホンダはこの核心部分の技術実証に成功したわけです。宇宙規模で見ればSpaceXやブルーオリジン(同じくアメリカの民間宇宙企業)がリードしている分野ですが、ホンダもついにそこに名乗りを上げ、「宇宙輸送システムの事業化に向けて一歩踏み出した形だ」と評価できます。
またホンダの強みとして見逃せないのは、異業種からの参入ならではの技術力です。自動車メーカーであるホンダは、エンジンや制御の分野で長年培ったノウハウがあります。そのおかげで、ロケットの開発にも独自のアプローチが生きています。例えば今回の実験機では、燃料ポンプやターボの羽根に航空機エンジンやレーシングカーの技術を応用し、姿勢制御には自動車の自動運転技術まで活用しているといいます。こうした多分野の技術融合は、純粋なロケット専業の企業にはない強みでしょう。実際、ホンダはF1エンジン開発などで培ったアジャイル開発(迅速な改良サイクル)の手法をロケット開発にも取り入れており、問題発生時の原因解析と改善を素早く回す工夫もしているそうです。その結果、2019年に研究開始してからわずか数年で今回の成功に漕ぎ着けたスピード感は特筆に値します。これは日本の民間宇宙開発の新たな可能性を示すものであり、国内外の宇宙業界からも「ホンダがついにここまで来たか!」と注目される快挙と言えるでしょう。
もちろん、現時点では小型実験機でのテスト成功に過ぎないため、宇宙全体から見れば第一歩です。しかし、その一歩は日本の宇宙開発史において大きな意味を持っています。他の国内民間企業では、例えば北海道のベンチャー企業が小型ロケットMOMOを打ち上げたりしていますが、いずれも使い捨て型で再使用は想定していません。ホンダは異色の存在として、この難しい再使用技術に真正面から挑み成果を上げたわけで、技術的チャレンジ精神と達成度において突出していると言えるでしょう。
今後の展望:商用化に向けてホンダはどう動く?
今回の実験成功を受けて、ホンダの再使用型ロケット開発は次のステップへ進みます。とはいえ現在はまだ研究段階であり、これをすぐ事業(商用サービス)にするかどうかは未定とされています。ホンダ自身、「事業化するかは決まっていないが、要素研究は続ける」とコメントしており、慌てず着実に技術を磨く姿勢です。そのうえで技術開発の目標として掲げられているのが、2029年までにロケットを宇宙空間(準軌道)に到達させる能力を実現することです。「準軌道」とは人工衛星が地球を回る軌道には達しないものの、高度100km前後の宇宙空間まで到達する飛行のことで、まずはそこまでロケットを飛ばして戻ってくるのが目標になります。そして2030年頃までには試験機を実際に宇宙に打ち上げ、人工衛星を運ぶ小型ロケットの商用化を視野に入れているとも報じられています。
簡単に言えば、ホンダは今後数年で数百メートル規模の実験から数十キロ、100キロといった高空間での試験へステップアップしていくと見られます。今回の300m級のホップ(跳躍)実験はその第一段階に過ぎません。宇宙空間に到達するには高度をさらに数百倍、高速も地球周回軌道に乗るためには音速の何十倍もの速度が必要で、技術ハードルは格段に上がります。それでも、まずは垂直離着陸という基礎技術の実証に成功したことの意義は大きいのです。この先ホンダはエンジン出力を上げたり機体を大型化したりしながら、より高く速い飛行実験に挑むでしょう。例えば次は数キロメートルの高度テスト、ゆくゆくは宇宙空間到達、最終的には衛星を軌道投入する“本物のロケット”へと段階的に開発を進めていくものと思われます。
もしホンダが計画通りに技術を確立できれば、2030年代にはホンダ製の小型ロケットが商用衛星を打ち上げる未来が現実味を帯びてきます。そうなれば、通信衛星や地球観測衛星をホンダが請け負って打ち上げる日が来るかもしれません。ホンダ自身、ロケットで人工衛星を上げることで自社の様々なサービスに繋げたいというビジョンも語っていました 。たとえば衛星による広域通信ネットワークで車のコネクテッドサービスを強化したり、衛星データを活用した気象・環境モニタリングでモビリティ運用を最適化したり、といったシナジーも考えられます。単に「ロケットを売る」だけでなく、ロケットを通じて自社の事業領域を拡げ、新たな価値を提供する可能性がある点は、ホンダならではの戦略と言えるでしょう。
ホンダの宇宙開発への参入は、日本のみならず世界的にも興味深い動きです。かつてロケット開発は国家機関の専売特許のような分野でしたが、近年はSpaceXやブルーオリジン、各国の新興企業など民間の力が宇宙開発を牽引する時代になっています。そこに自動車メーカーという異業種のホンダが加わったことで、宇宙ビジネスの裾野はさらに広がりを見せています。競争が激化すれば技術革新も加速し、コスト低減が進んで私たち一般人にとっても宇宙が身近になるかもしれません。ホンダの掲げる「The Power of Dreams(夢の力)」は、いよいよ地球を飛び出して宇宙へ向かおうとしています。今回の成功はその夢への第一歩。今後、ホンダのロケットが実際に人工衛星を載せて宇宙へ飛び立つ日が来るのを、私たちもワクワクしながら待ちたいですね。
もっとホンダを知りたい方へ:おすすめ本・アイテム紹介
今回の再使用型ロケット実験をきっかけに、ホンダに興味を持った方のために、ホンダの精神や技術に触れられる本やグッズをご紹介します。
- 『本田宗一郎 夢を力に』 ホンダ創業者の哲学や挑戦の原点を知ることができる自伝的作品。夢を現実に変える力とは何かを教えてくれます。
- 『ホンダ イノベーションの神髄』 オックスフォード大学教授による、ホンダの革新力を体系的に分析した書籍。経営・組織の観点からホンダの強さを読み解く内容で、非常に読み応えがあります。
- HondaJet(ホンダジェット)関連グッズ:ホンダが開発した小型ビジネスジェット機「HondaJet」の模型や公式グッズ。空への挑戦が形になった象徴的存在です。
- ASIMO(アシモ)関連グッズ:ホンダの二足歩行ロボット「ASIMO」のフィギュアや書籍など。未来志向のテクノロジーに興味がある方におすすめ。
- 技術者ドキュメンタリー(情熱大陸など):若手エンジニアがホンダで夢を実現していく姿を追ったドキュメント番組。リアルな現場の熱量が感じられます。
- ホンダコレクションホール(栃木県):ホンダの名車・名機がずらりと並ぶ公式ミュージアム。HondaJetやASIMO、F1マシンまで見学可能。未来のロケット展示にも期待!